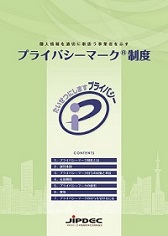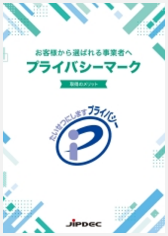社会保険労務士法人ミライエ
- トップページ
- 審査基準・指針
- 付与事業者の取組事例
- 社会保険労務士法人ミライエ
2025年8月18日掲載
個人情報の適切な取扱いが、取引先の企業とそこで働く従業者との信頼関係につながる

企業にかかせない存在である社会保険労務士。「社会保険労務士法人ミライエ」は、人事労務相談・労働社会保険の各種手続き・人事コンサルティングなど、多岐にわたる業務を担っています。業務の特性上、取引先の企業から膨大な量の個人情報を預かり、取り扱う同社がどのようにPマークを活用し、PMSを運用しているのかをお話いただきました。
お話を伺った代表社員 兼 CEO 根本 啓明様(写真右から2番目)、代表社員 兼 COO 石上 慶様(写真右)。
会社概要
社会保険労務士法人ミライエ
本社の所在地:東京都千代田区永田町二丁目11番1号
2013(平成25年)年設立/従業員数9名(2025年7月時点)
人事・労務に関する各種事務手続き(社会保険・給与計算等)から人材育成体系構築・就業規則改正・社内研修講師・労使協議・労使トラブルの解決まで、人事・労務全般に精通している社会保険労務士法人。
取り扱う個人情報
- 取引企業の従業者の情報
- 自社従業者の情報など
- Pマーク付与…2015年10月9日、登録番号…10840552 (06)
インタビュー
法改正とマイナンバー制度の開始により、Pマークの取得を決意
2015年にPマークを取得されていますが、その当時に取得に至った経緯や背景、目的について伺えますか?

ミライエを創業したのは2013年で、その年には社労士事務所向けの個人情報保護認証制度であるSRP認証を取得し、個人情報の取扱いには配慮していました。その後2年が経過し、取り扱う個人情報が増えてきたこともありますが、最大のきっかけはマイナンバー制度の開始です。また、同年には個人情報保護法の改正もあり、取扱いの件数に関わらずすべての事業者に法律への対応が求められるようになりました。
これらをきかっけに、個人情報の適切な取扱い体制を整えることで、自ずとPマークも取得できるのではないかと考え、取得の取組みを始めました。結果的には2015年10月中(※)に取得ができたので、良いタイミングでの決断だったのではと思っています。
※マイナンバーは2015年10月から各個人宛への通知書の送付、翌年2016年1月からマイナンバー制度の運用が開始されました。
社労士事務所が取り扱われる個人情報の量は膨大ですよね。取得には苦労されたのではないですか。
他の士業さんと比べますと、圧倒的に個人情報を取り扱う量が多いです。私たちが取得に取り組んだのは創業2年目の2人しかいない時代で、個人情報の取扱いもまだ少ない段階でした。この段階であれば、規定やルール、手順も作りやすいと考え、早く着手した方がいいのではと取得を決意しました。Pマークは2人以上いれば申請ができるので、当然取りにいくべきマークだと捉えており、そういった点も取得のきっかけの一つでした。
Pマークが営業ツールの役割を担うことも
Pマークの取得によって、どのような効果やメリットがありましたか?
社労士事務所は、クライアントの企業で働く従業員の個人情報を利用し、申請・手続きを行って、利益を得る業態です。また、私たちにとって個人情報は、価値創造の源泉となる重要資産です。Pマークの取得によって、個人情報の価値に対する意識を改めて持つことができ、より大切に取り扱う土壌ができました。
そして、これは社労士事務所限定のメリットではありますが、Pマークを取得しているとSRPⅡ認証制度の申請手数料が無料になります。これは非常にありがたいです。
対外的には、クライアントがPマークを持っている場合に、委託先の評価においてPマークを取得していることが評価され、説明が簡素化されるメリットがあります。実際に受託をした際にも「Pマークを持っていることが一つの選定基準になりました」とおっしゃっていただいたことがありました。そういった意味では、Pマークが営業ツールにもなっていると感じます。
Pマークは第三者の客観的な審査を受けた結果が視覚的にあらわれるものなので、対外的にもシンプルでわかりやすい。ホームページにもPマークを掲載しているため、新規委託を検討されている企業に対して個人情報の管理体制を細かに説明しなくても、安心感を持っていただけています。
属人化を避け、シンプルな運用を考える
PMS運用において、社内教育はどのように取り組んでいますか。
社労士事務所では個人情報を取り扱うことが日常業務になりますので、採用の際には入職初日に研修を実施し、業務を開始する前の段階で、意識づけを行うように工夫しています。
定期的な研修では、プライバシーマーク制度のホームページで公開されている社内教育用動画を利用し基本を学びます。その後、実際に個人情報を取り扱う場面を想定しながら、誤送信や誤入力の防止、複眼での確認の徹底など、管理体制の説明をするようにしています。
仕事の方法についても、属人化することでPMSの運用から外れた方法になってしまわないように、責任者を中心に業務のローテーションを行いながら平準化を図っています。また、全国社会保険労務士会連合会が定期的に実施している「標的型の攻撃メール訓練」にも積極的に参加し、社内の意識を高めています。
その他、御社ならではの工夫されている点や取り組みがありましたら、伺えますか。
まずは、紛失・盗難や廃棄時のリスクを低減するためにペーパーレス化を進めています。紙にしてしまうと業務が属人的になる恐れや、特定の人しか持ち得ない資料が存在してしまうことも起こりえますので、そのようなリスクを回避するためでもあります。
安全管理の面では、Pマークの初回更新の2017年にセキュリティレベルが高い建物に事務所を移転し、物理的な安全管理をより強固にしました。
業務においては、業務の流れを極力シンプルにするように工夫をしています。一般的な社労士事務所には、郵送やFAX、メールなど様々な方法で情報が入ってくることが多いのではないでしょうか。ミライエの場合は初めから取り扱う方法を決めて、社内へ入ってくる情報のルートを限定し、システムにはデータを取り込むという形で誤入力などのミスを防ぐようにしています。業務をシンプルにすると運用が楽になる面もありますし、結果的には効率化にもつながります。このような体制作りや社内教育を通して業務の品質向上を図ることで、クライアントからの信頼を得られるようになったと感じています。
PMS運用で苦労されている点はありますか。

新しいサービスの導入を検討する際に、新たな情報の保管先や手順が増えることへの懸念が頭をよぎることです。業務において効率が良い方法があったとしても、代わりに個人情報保護においてのリスクが高くなる場合には断念することもあり、効率と個人情報の取り扱いのバランスをとることに苦労していますね。個人情報の保管・送信等に利用するツールも、Pマーク取得企業やISMAPの登録を受けているクラウドサービスを選定するようにしています。私たちは常にPマークを意識しているので、ある面では重石になっていることもあるかもしれません。ですが、良い意味では歯止めとして機能していると思います。
その他の点で、Pマークの取得や維持をするために多くの企業がハードルと感じているのは、2年に1度の審査ではないかと思います。しかし、私たちはこの審査を外部の専門家の目が入る貴重な機会と捉えています。
PMSの運用は自分たちで検討しリスク分析や内部監査を行いますが、定期的に外部からの審査が入ることはとても大事なことです。審査員の方から運用について悩んでいることに意見をもらえる場合もあり、そういったお話を通して私たちも改めて考えたり安心できたりしています。審査時の指摘事項や継続的改善事項も、PMS運用の改善につなげていけますし、審査に関してはすごくいい機会だと思っています。
ヒューマンエラーの削減と業務の更なる効率化を目指して
今後の課題やPMSを継続運用していく上で注力していきたい点などがあれば、教えてください。
今後の課題としては、ヒューマンエラーを極力減らすことです。手作業によるデータ入力は、誤った個人情報の登録につながることから、現在一部の業務でRPA(業務の自動化)を導入し、データ入力や公文書保存時のヒューマンエラー削減に努めています。ヒューマンエラーはクライアントの従業者にも不利益が発生し得ること、そして業務効率を下げる要因にもなります。その点で作業の一部をRPA化することは有効です。
今後も個人情報保護法の改正や構築・運用指針の改定に合わせたPMS運用の改善を進め、電子手続きの更なる拡大やクラウドサービスの発展など、社会動向を的確にとらえた業務の効率化も進めていきたいと考えています。
最後にプライバシーマーク制度に対するご要望を伺えますか。
社労士事務所は、B to B取引が主のため、クライアントの信頼を得ることを目的にPマークを取得していますが、世間では一般消費者向けにマークを示していることをよく目にします。一般消費者の方々の個人情報保護の意識が高まってきている中で「この企業なら安心して自分の情報を預けられる」と考える方が増えていくといいなと思います。Pマークは何を示しているかがわかりやすく、伝わりやすいマークだと思うので、Pマークを表示する会社も増えてくれるといいなと。今後そういう世の中になってくれると嬉しいです。
そして、Pマークは申請をすれば取得できるマークではなく、外部の審査を受けた上で評価されているマークなので、そういう面が一般消費者にしっかり伝わるようになることを期待しています。
資料ダウンロードはこちら
-
制度全般パンフレット
-
事業者向けリーフレット