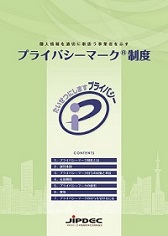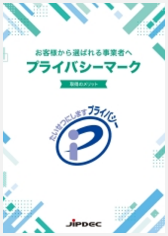【2025年度】インタビュー特別企画
- トップページ
- 審査基準・指針
- 付与事業者の取組事例
- 株式会社Works Human Intelligence
2025年7月17日掲載
株式会社Works Human Intelligence

会社概要
株式会社Works Human Intelligence
本社の所在地:東京都港区赤坂1丁目12−32 アーク森ビル 21F
2019年8月1日設立/社員数 2,198人(連結) ※2024年12月末時点
- 業種:情報サービス・調査業
-
Pマーク付与…2019年9月24日、登録番号…22000323(04)
審査機関:一般社団法人ソフトウェア協会
取り扱う個人情報
- お客様向けサービスに係る情報
- 取引企業の情報
- 採用応募者の情報
- 自社従業者の情報など
インタビュー
インタビュー回答者
-

申請担当者:渡部 裕様 -

個人情報保護管理者:津田 桃子様 -

教育担当者:保科 亜由望様
- Q
プライバシーマーク導入の背景を教えてください
- A
現在は、個人情報保護法だけを守っていればよいという時代ではなく、個人のプライバシーに配慮した対応が必要になっていると感じています。その意味では、本人のプライバシーをはじめとする基本的な権利を損なうことのないよう、企業が適切な対応を行うことを目的とするプライバシーマークは、個人情報保護法よりひと回り大きな枠組みでのマネジメントシステムを構築できるため、メリットが大きいと考えています。
当社ではHR領域でお客様にサービスを提供している関係で、社内におけるリスクマネジメントは当然のことながら、お客様からの信用獲得のためにもプライバシーマークの取得は重要と捉えています。
導入の目的
・個人情報保護法より高い水準でマネジメントシステムを構築するため
・顧客からの信頼の獲得
- Q
取得に至るまでの過程やPMS維持する中で、ご苦労された点はありますか
- A
当社は前身の会社の時からプライバシーマークを取得していたので、それほど迷いも苦労もありませんでした。
但し、当社はプライバシーマークの他に、多くのISO認証(ISO27001、ISO27017、ISO27701)を取得している関係で、複数の台帳作成を行う必要があり、担当部門の工数が大きかったのも事実です。
そのため、昨年からは3つあった台帳をひとつに統合するプロジェクトを立ち上げ、統合版台帳に集約することができました。これからも引き続き改善を推進し、さらに統合できる範囲を広げていきたいと考えております。
- Q
プライバシーマーク取得後にどのような効果がありましたか
- A
当社では、各部門から情報資産管理担当者を選任し、個人情報を含む情報資産管理やリスクアセスメント等を担当してもらっています。この情報資産管理担当者が核となって、毎年部門内での改善活動や課題・リスクの抽出、リスクへの対応計画の策定を行い、全社で個人情報の保護に取り組んでいます。これらの取組みにより、強固な個人情報保護の体制構築につながりました。
さらに、トップマネジメントがマネジメントレビュー等を通じて、具体的なリスク対策や教育施策への指示を率先して行うなど、陣頭指揮に立つ意義は大きく、全従業者の個人情報保護やプライバシー対する意識向上の起点になっています。
毎年、プライバシーマークの個人情報保護マネジメントシステム(PMS)を実施するという前提がなければ、このような個人情報保護の体制維持は実現できないのではないかと考えています。
取得の効果
・個人情報保護体制の強化
・従業者の個人情報保護意識の向上
- Q
PMSの運用において、工夫している点があれば教えてください
- A
・従業員教育の工夫
自社で想定される事故を動画で再現したり、「自分はできているか?」という自己チェックを必須にすることで、受講者が自分ごととして捉えられるように工夫をしています。さらに、今期は単なる正誤テストではなく、生成AIを活用したセキュリティアドバイザーとの対話形式を取り入れ、能動的かつインタラクティブな教育を実現しています。
・内部監査の工夫
内部監査ではGoogle Workspaceの連携機能を活用して、日程調整や監査記録の集計、レポート作成を自動化しています。また、オンラインの監査実施やビジネスチャットツールを活用し、被監査各部門の負担低減に努めています。
- Q
PMSの運用について、今後の課題や目標があれば教えてください
- A
日々個人情報の保護を意識し、自社のPMSに倣って管理・改善するという習慣は社員にも根付いてきていると感じます。生成AIの利活用など、変化の多い時代になっていますが、今後もプライバシーマークの枠組みや基準を活用しながら、しっかりPDCAを回していきたいと考えています。
他に重要なポイントとして、「審査を通過するのが目的ではない」という意識を持つことです。以前は、審査の際に指摘事項をいただくと少々気落ちしたものですが、最近では「ありがとうございます」と心の中で叫んでいます。本当ですよ。
資料ダウンロードはこちら
-
制度全般パンフレット
-
事業者向けリーフレット